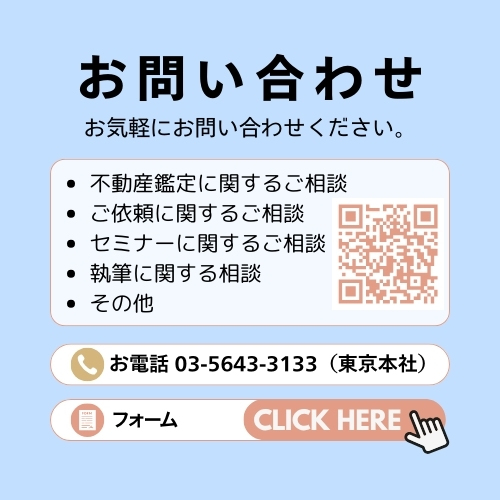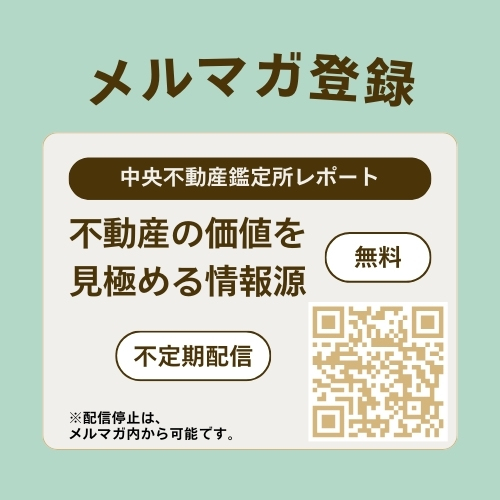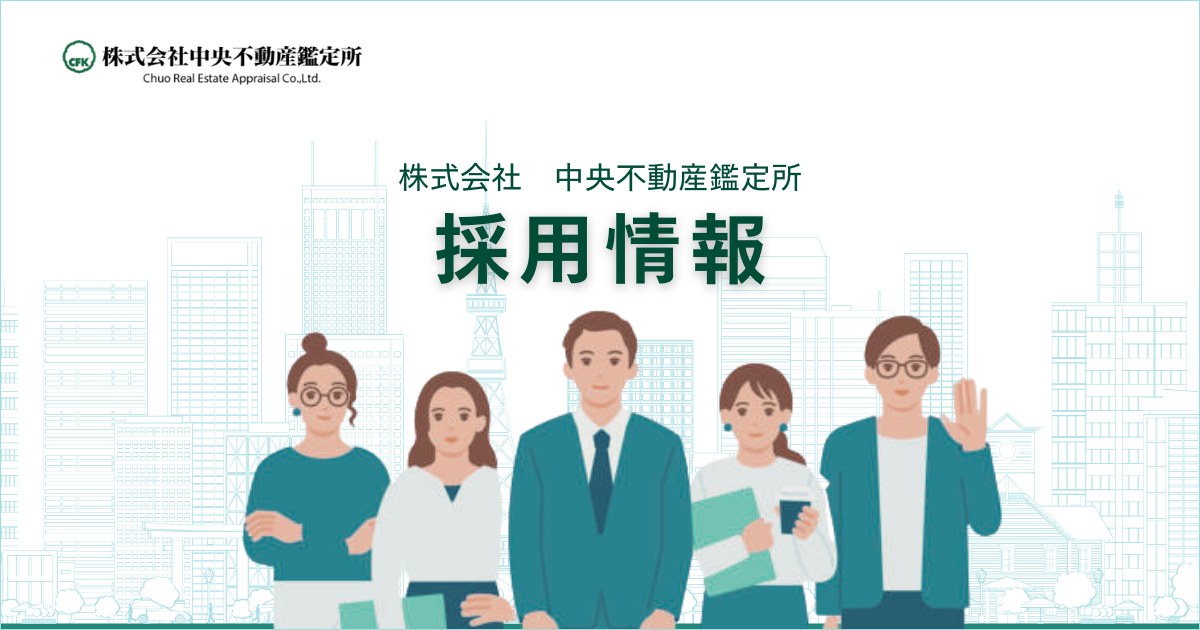原賃貸借契約のことをいい、物件(ビル・マンション等)の所有者と転貸を行う者(管理会社等)が締結する。アセットファイナンスのセール&リースバック型では、オリジネーター(原所有者)は、所有権を信託譲渡した信託銀行より、賃借人として賃借し、一部テナントの入っている物件の場合には、一括賃借のうえテナントに転貸する。この場合のオリジネーターと信託銀行との契約をマスターリース、オリジネーターとテナントとの契約をサブリースという。現在は信託銀行(マスターレッシー)とサブリースを行う管理会社等との契約が多くなっている。なお、証券化の場合は、エンドテナントからの賃料は、サブリース、マスターリースへと流れるが全額がオーナーへ渡るパススルーと方式が主流である。
一般的なマスターリース方式の概要は以下のとおりである。
1. マスターリース方式の仕組み
マスターリース方式では、不動産会社(サブリース会社)がオーナーから物件全体を一括で借り上げ、入居者に転貸する形をとる。
オーナーとサブリース会社の間で賃貸借契約を結び、サブリース会社が入居者との賃貸契約を管理する。
【基本的な流れ】
オーナー → サブリース会社
・一括借上げ契約を締結
・サブリース会社は、物件の空室状況に関わらず、オーナーに一定の賃料を支払う(保証賃料)。
サブリース会社 → 入居者
・入居者を募集し、契約を締結
・実際の家賃はサブリース会社の収益となる。
2. マスターリース方式のメリット
(1) オーナーにとって
空室リスクの軽減
空室があっても、サブリース会社から一定額の賃料が支払われる。
管理の手間が削減
入居者募集・家賃回収・トラブル対応などをサブリース会社に一任できる。
キャッシュフローの安定
長期的に収益が見込みやすく、ローン返済計画が立てやすい。
(2) サブリース会社にとって
転貸による家賃差益を得られる。
大規模な管理物件の獲得により、スケールメリットが働く。
3. マスターリース方式のリスク・注意点
(1) 家賃減額リスク
サブリース会社は契約時に「家賃は将来的に見直し可能」としているケースが多く、数年ごとに保証賃料が下げられることがある。
特に人口減少エリアや老朽化物件では、このリスクが高い。
(2) 契約解除リスク
サブリース会社が赤字経営に陥った場合、契約解除や倒産のリスクがある。
その場合、オーナーは直接入居者と交渉する必要が生じる。
(3) 賃料差益の減少
サブリース会社が入居者から受け取る賃料とオーナーへの保証賃料の差額が大きい等、オーナーの収益が大きく削られる契約があることに留意*しなければならない。
*マスターリース方式に関するトラブル(不動産の証券化を除く)が増えたため、国土交通省は2020年6月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリース新法)」を施行した。