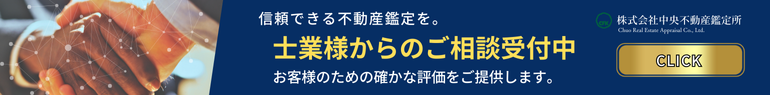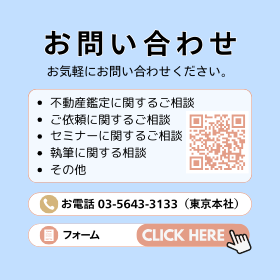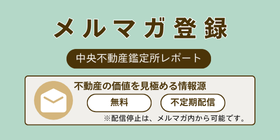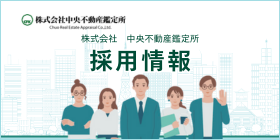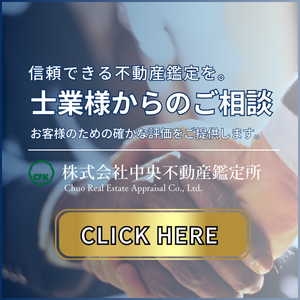相続は一度で終わるものではなく、親から子への「一次相続」に続き、配偶者が亡くなった際には「二次相続」が発生します。
特に二次相続では、一次相続で利用できた配偶者控除などの制度が適用できない場合が多く、
相続税の負担が大きくなりやすいのが特徴です。
本記事では、二次相続の基本的な仕組みから、起こりやすいトラブル、税負担を抑えるための具体的な対策までを解説します。
二次相続とは?一次相続との違い
二次相続とは、一次相続で配偶者が受け取った財産を、その配偶者が亡くなったときに子どもなどが相続することです。
一次相続では配偶者控除などを利用できる一方、二次相続では適用が難しくなるケースが多く、相続税が増える要因となります。
二次相続が発生する流れ
一次相続で遺産を受け取った配偶者が亡くなったときに二次相続が発生します。
遺産の把握、分割協議、協議書作成、不動産の相続登記、相続税の申告・納税といった流れを経ます。
特に不動産相続は分割が難しいため、早めの準備が欠かせません。
税額が変わる理由
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
一次相続時は相続人が多く控除額も大きいのに対し、二次相続では相続人が減り控除額も減少するため、税額が増えやすくなります。
さらに、一次相続で使えた配偶者控除や小規模宅地等の特例が二次相続では利用できないケースが増え、結果として負担が重くなりがちです。
一次相続で見落とされがちな問題点
一次相続で配偶者がすべての財産を相続すると、二次相続時に子ども同士での分割が困難になり、トラブルが生じやすくなります。
また、配偶者控除を最大限利用すると、二次相続で課税額が急増することもあります。
二次相続のデメリットとは
二次相続には、一次相続にはない特有のリスクが存在します。
最大のデメリットは、相続税の負担が大きくなりやすい点です。
一次相続では配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用できるため税額を抑えられますが、
二次相続ではこれらの制度を使えない場合が多く、結果として課税対象となる資産が一気に膨らむことがあります。
また、一次相続の際に配偶者へ資産を集中させると、二次相続時にその財産全体が課税対象となり、
納税資金の確保のために不動産を急いで売却せざるを得ない状況に陥ることもあります。
さらに、二次相続では相続人の数が減少するため、基礎控除額が小さくなるのもデメリットです。
例えば、父の一次相続時は「母+子ども2人」の3人で相続した場合、控除額は4,800万円ですが、
母が亡くなって子ども2人だけで相続する二次相続では4,200万円まで下がります。
不動産相続が含まれる場合には、分割の難しさや維持管理費の負担も加わり、
親族間でのトラブルにつながるケースが多い点も見逃せません。
こうした不動産の評価や分割方法を適切に検討しないと、余計な税負担や「争族」の火種を残すことになります。
中央不動産鑑定所では、不動産の正確な評価を通じて、適切な遺産分割や相続税対策のプランニングをサポートしています。
二次相続のデメリットを事前に把握し、最適な対応をとることが、ご家族の安心と資産の保全につながります。
▶︎不動産相続放棄はできる?手続き・費用・注意点をわかりやすく解説します。
二次相続で発生しやすいトラブルとは
【要点】
- 不動産の共有名義による分割トラブル
- 遺言書がない、または内容が曖昧なことによる「争族」
- 相続登記を放置した場合の法的リスク
- 少額遺産でも意見対立が起きやすい
不動産の共有名義による分割トラブルは、特に二次相続で多く発生します。
複数の相続人で不動産を共有すると、売却や利用方法をめぐって意見が一致しにくく、
結果として遺産の処分が進まないことも少なくありません。
遺言書がない、または内容が不明確な場合には、親族間で公平性をめぐる不満が表面化しやすく、
いわゆる「争族」と呼ばれる争いに発展するリスクがあります。
▶︎その他の分割方法についての記事はこちらをクリックしてください。
遺言があっても法的要件を満たしていないと無効になる可能性があるため、専門家による確認が欠かせません。
さらに、相続登記を放置してしまうと、名義が被相続人のままとなり、権利関係が複雑化します。
これにより不動産を売却できなくなったり、第三者による差し押さえのリスクを抱えることもあります。
2024年からは相続登記の義務化が進んでいるため、対応を怠ると法的ペナルティが科される点にも注意が必要です。
また、少額の遺産であっても、預貯金や小規模な不動産をどう分けるかで対立することは珍しくありません。
特に、手続きにかかる費用が遺産額に比べて大きい場合、「相続を続けるか放棄するか」で意見が割れやすくなります。
税負担を抑えるための対策
【要点】
- 不動産や資産を均等に分割する工夫
- 配偶者控除の使い方に注意する
- 生前贈与を計画的に活用する
- 家族信託や遺言信託で資産管理を明確化
- 不要な不動産を売却して納税資金を確保する
不動産や資産を均等に分割する工夫は、相続人全員が納得しやすい形を作るために有効です。
例えば、不動産を複数の子どもで共有するのではなく、一人が取得して他の相続人には代償金を支払う形にすれば、将来のトラブルを防げます。
配偶者控除は一次相続で強力な節税策となりますが、配偶者が多くの財産を相続すると、二次相続で子どもたちの税負担が跳ね上がる場合があります。控除を使う際には、二次相続の影響も考えたバランスが重要です。
生前贈与は、資産をあらかじめ少しずつ子どもや孫に移転することで、二次相続時の課税対象額を減らせます。
年間110万円の基礎控除を利用した暦年贈与や、相続時精算課税制度を組み合わせれば、効率的に資産を移せます。
なお、贈与加算は2024年以降の贈与から「死亡前7年間」に延長されるため、早めの準備が重要です。
家族信託を活用すれば、誰がどのように不動産や資産を管理するかを事前に定められるため、
二次相続後の争いを未然に防ぐことができます。
また、遺言信託を利用すれば被相続人の意向を確実に反映させることが可能です。
さらに、不要な不動産を売却して現金化しておけば、相続税の納税資金を確保しやすくなります。
賃貸経営に活用すれば、納税資金の準備と資産の有効活用を両立することも可能です。
小規模宅地等の特例といった制度を組み合わせることで、税負担を大きく減らすこともできます。
円満な相続のために
家族会議で資産や維持費を共有し、具体的な管理方針を話し合うことが大切です。
さらに、遺言書を作成して財産の分配を明確にしておけば、親族間の争いを防ぎやすくなります。
相続税や不動産評価に詳しい専門家へ相談することで、税負担を抑えつつ安心できる相続を実現できます。
まとめ
二次相続は、一次相続に比べて相続税の負担が大きくなりやすく、手続きも複雑です。
特に不動産相続では、分割の難しさや登記の義務化などが絡み、親族間のトラブルに発展するリスクも少なくありません。
こうした問題を回避するためには、一次相続の段階から二次相続を見据えて計画を立てることが重要です。生前贈与や信託の活用、相続税のシミュレーションなど、事前にできる対策は多くあります。
中央不動産鑑定所では、不動産の正確な評価をもとに、円滑で安心できる相続の実現をサポートしています。
二次相続や不動産相続に不安をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
ご家族の大切な資産を守るために、最適な解決策をご提案いたします。