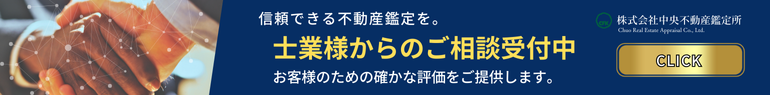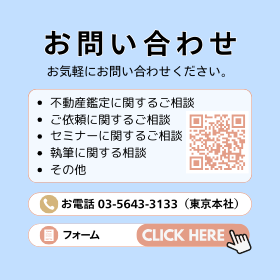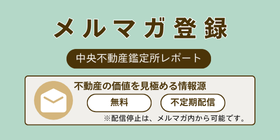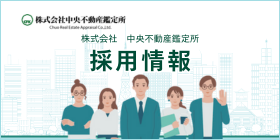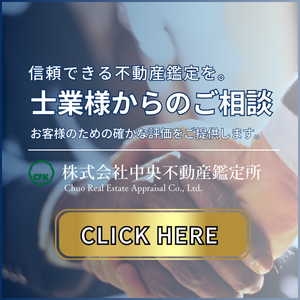子どもがいない夫婦にとって、将来の遺産相続は大きな関心事のひとつです。
「配偶者がすべてを相続できるだろう」と漠然と考えていても、実際には親や兄弟姉妹が相続人となり、
思わぬ形で財産を分けることになるケースも少なくありません。
特に不動産が関わる場合には、相続人間での調整が難しく、トラブルに発展するリスクも高まります。
この記事では、子どもがいない夫婦の相続に関する基本的なルールから、
誤解されやすいポイント、そして円滑に進めるための具体的な対策までを解説します。
子どもがいない夫婦の遺産相続で気をつけたいこと
子どもがいない夫婦の相続では、「配偶者がすべての財産を受け継ぐ」と考える方が少なくありません。
しかし実際には、被相続人の親や兄弟姉妹も相続人になる場合があり、配偶者だけで全財産を相続できるわけではありません。
そのため、相続人の範囲や取り分を正しく理解し、事前に対策を講じることが重要です。
相続人の範囲と配偶者の権利
配偶者は常に相続人
日本の民法では、配偶者は常に相続人となります。これは子どもの有無や親族の有無にかかわらず変わりません。
ただし「配偶者だけが相続人になる」とは限らず、他の親族が相続に加わる場合があります。
親が相続人となる場合の取り分
子どもがいない場合、被相続人に親が存命であれば、配偶者と親が相続人となります。
取り分は配偶者が三分の二、親が三分の一です。
配偶者にとっては多くの割合を相続できるものの、不動産など分割が難しい財産があると調整が難航するケースもあります。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケース
親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
この場合、配偶者の取り分は四分の三、兄弟姉妹は四分の一です。
さらに兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、その子どもである甥や姪が代襲相続人となります。
相続人の範囲が広がると協議が複雑になりやすいため注意が必要です。
法定相続順位とよくある誤解
「配偶者が全財産を相続できる」という誤解
「子どもがいなければ配偶者がすべてを相続できる」と考えるのは誤解です。
親や兄弟姉妹がいれば彼らも相続人となり、財産を分ける必要があります。
「兄弟姉妹が配偶者より優先する」という誤解
配偶者は常に相続人であり、兄弟姉妹が配偶者に優先して相続することはありません。
相続順位は、子どもが第一順位、親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位と定められています。
兄弟姉妹には遺留分がないことに注意
相続では遺留分という最低限の取り分が認められていますが、兄弟姉妹にはこの権利がありません。
したがって遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と記してあれば、兄弟姉妹は相続できないこともあります。
子どもがいない夫婦の相続で起こりやすいトラブル
不動産の分割をめぐる対立
不動産は分割が難しいため、共有状態になると使用や売却をめぐってトラブルが生じやすい財産です。
配偶者が住み続けたいと考えても、兄弟姉妹や甥姪が売却を求めると対立が起こる可能性があります。
協議の長期化と親族関係の悪化
相続人が複数いる場合、遺産分割協議が長期化することも珍しくありません。
誤解や不信感が積み重なることで、親族関係そのものが悪化してしまうリスクもあります。
スムーズに相続を進めるための解決策
遺言書を作成するメリット
遺言書を作成しておけば、法定相続分ではなく被相続人の意思に沿った財産分割が可能です。
配偶者を優先的に守りたい場合には最も有効な手段となります。
生前贈与を活用する際の注意点
財産を生前に贈与することで相続時のトラブルを防ぐことができます。
ただし年間110万円を超える贈与には贈与税が課されるため、制度を正しく理解する必要があります。
家族信託を利用する方法
家族信託は、財産管理と相続をスムーズに行うための新しい仕組みです。
信託契約を結ぶことで、配偶者を受益者に指定し、生活資金を安定的に確保できます。
将来を見据えた相続準備
共有名義の財産を整理する
夫婦で共有名義にしている財産は、相続時に権利関係が複雑化します。
生前に名義を整理し、配偶者が確実に生活基盤を維持できるようにしておくことが望ましいです。
生命保険を活用して配偶者を守る
生命保険金は相続財産とは別に扱われるため、確実に配偶者の手に渡ります。生活費や住居費の確保に有効な方法です。
元気なうちに備える重要性
遺言書の作成や家族信託の検討は、健康で判断能力があるうちに行うのが理想です。早めの対策が配偶者の安心につながります。
まとめ
子どもがいない夫婦の相続では、配偶者がすべてを相続できるとは限らず、親や兄弟姉妹、甥や姪が相続人になるケースもあります。
こうした状況は親族間のトラブルを招きやすいため、遺言書や生前贈与、家族信託などを活用して早めに備えることが大切です。
専門家に相談しながら準備を進めれば、配偶者の生活を守り、相続後も親族関係を良好に保つことができます。
不動産相続において特に重要なのが、不動産の正確な評価です。相続財産の中でも不動産は大きな割合を占め、評価額次第で相続税額や分割方法が大きく変わります。
不動産鑑定士に依頼することで、適正な時価評価を行い、節税やトラブル防止につなげることが可能です。
また、鑑定評価書は法的効力を持つため、親族間での公平な分割を実現し、紛争を未然に防ぐ役割も果たします。
中央不動産鑑定所では、相続や不動産取引に関する豊富な実績を持つ鑑定士が、正確かつ中立的な評価を提供しています。
相続を円滑かつ安心して進めるためには、専門家の知見を取り入れることが欠かせません。
不動産相続でお悩みの際は、ぜひ中央不動産鑑定所にご相談ください。
▶︎ 不動産相続を成功に導くために不動産鑑定を利用する4つのメリットとは?