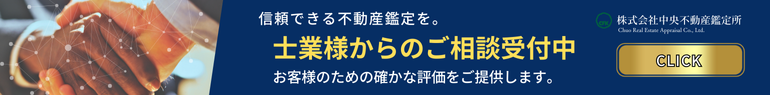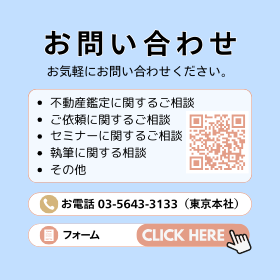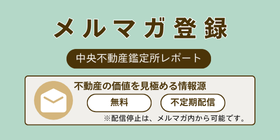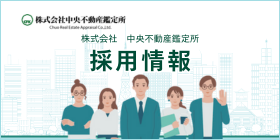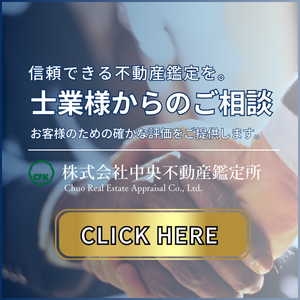相続をきっかけに不動産を売却する方は少なくありません。
しかし、「相続不動産を売却した場合に確定申告が必要かどうか」は多くの人が迷うポイントです。
利益が出れば課税対象になりますが、損失や少額の場合には申告が不要になるケースもあります。
また、特例や控除を使うときには、たとえ利益が出ていなくても確定申告をしなければなりません。
申告を怠れば延滞税や加算税といったペナルティが課される可能性もあります。
本記事では「不動産相続 売却 確定申告」をテーマに、必要なケース・不要なケース、税金の計算方法や注意点まで徹底的に解説します。
相続不動産を売却したら確定申告は必要?
結論として、相続不動産を売却した際の確定申告は次の三つの基準で判断できます。
- 売却益があれば必ず申告が必要
- 損失でも特例を利用するなら申告が必要
- 少額の所得なら免除される場合もあるが、住民税は別途確認が必要
売却益があれば必ず申告が必要
相続不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は、確定申告が必須です。
譲渡所得は「売却価額-(取得費+譲渡費用)」で計算され、プラスであれば課税対象となります。
所有期間によって税率が変わり、長期譲渡(5年超)は約20.315%、短期譲渡(5年以下)は約39.63%です。
相続の場合、所有期間は被相続人が取得した時点から通算されるため、多くのケースで長期譲渡となります。
損失でも特例を利用するなら申告が必要
不動産の売却で損失が出た場合は、通常なら確定申告は不要です。
しかし「マイホームの譲渡損失の損益通算・繰越控除」といった特例を利用すれば、損失を他の所得と相殺したり翌年以降に繰り越せます。
相続不動産は原則対象外ですが、「空き家の3,000万円控除」や「相続税の取得費加算」といった制度を活用する場合も、確定申告が必要になります。
少額の所得なら免除される場合もあるが、住民税は別途確認が必要
会社員など給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下であれば所得税の申告が不要とされています。
ただしこれは所得税に限った特例で、住民税については別途申告が必要な場合があるため、油断は禁物です。
相続不動産の売却で確定申告が必要なケース
確定申告が必ず必要となるのは次のような場合です。
- 売却益(譲渡所得)が発生した場合
- 相続税の取得費加算の特例を利用する場合
- 空き家の3,000万円特別控除を利用する場合
- 居住用財産の譲渡損失特例を利用する場合
- 複数の相続人で換価分割を行った場合
売却益(譲渡所得)が発生した場合
売却価額が取得費や譲渡費用を上回ると譲渡所得が発生します。プラスであれば課税対象となり、必ず確定申告が必要です。
相続税の取得費加算の特例を利用する場合
相続税を支払った場合、その一部を取得費に加算できる制度があります。
譲渡所得を少なくできるため節税になりますが、適用を受けるには確定申告が欠かせません。
空き家の3,000万円特別控除を利用する場合
被相続人が居住していた空き家を売却した場合、条件を満たせば最大3,000万円まで控除可能です。
令和6年からは相続人が3人以上いる場合、控除額が2,000万円に縮小されているため注意が必要です。
居住用財産の譲渡損失特例を利用する場合
自宅を売却して損失が出た場合に使える特例で、損益通算や損失の繰越控除が可能です。
自分が住んでいた家が対象となるため、相続不動産には原則使えませんが、該当するなら申告は必要です。
複数の相続人で換価分割を行った場合
遺産分割前に不動産を売却して現金化する場合、各相続人に法定相続分どおりの譲渡所得が生じます。
それぞれが確定申告を行わなければなりません。
相続不動産の売却で確定申告が不要なケース
次のような場合には申告が不要となることがあります。
- 売却益が発生しなかった場合
- 取得費が譲渡価格を上回る場合
- 給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合
売却益が発生しなかった場合
売却価額が取得費や譲渡費用と同額かそれ以下であれば、譲渡所得はゼロまたはマイナス。
課税されないため申告は不要です。
取得費が譲渡価格を上回る場合
取得費が譲渡価格より高い場合も譲渡所得はマイナスとなり、課税対象になりません。
ただし、損失を特例で活用するなら申告が必要になります。
給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合
会社員など給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の申告は免除されます。
ただし住民税の申告が必要になる場合があるため、役所に確認しておきましょう。
相続不動産売却の税金と計算方法
税金の仕組みは以下の通りです。
- 譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費+譲渡費用)
- 取得費が不明な場合は売却価額の5%を概算で計上可能
- 所有期間5年超は長期譲渡(税率20.315%)、5年以下は短期譲渡(39.63%)
【計算例】
売却価額5,000万円、取得費1,500万円、譲渡費用300万円の場合
譲渡所得=5,000万円-(1,500万円+300万円)=3,200万円
確定申告に必要な書類と流れ
確定申告の際には以下の書類を準備します。
- 確定申告書B様式+分離課税用
- 譲渡所得内訳書
- 売買契約書、仲介手数料の領収書、登記事項証明書
- 相続税申告書や納税証明(取得費加算を使う場合)
手続きは税務署で提出するか、e-Taxでオンライン申告が可能です。
マイナポータルと連携すれば控除証明などのデータ入力が自動化され、手続きがスムーズになります。
確定申告を怠った場合のリスク
確定申告を行わなかった場合の主なペナルティは以下の通りです。
- 無申告加算税(期限後の申告に対する加算)
- 延滞税(納付の遅れに応じて発生)
- 重加算税(意図的な隠ぺいが認められた場合)
これらはいずれも余計な出費につながるため、必ず期限内に正しく申告することが重要です。
節税のために活用できるポイント
相続不動産を売却する際には、次のような節税対策が考えられます。
- 空き家の3,000万円特別控除の適用を検討する
- 相続税の取得費加算を利用する
- 長期譲渡になるよう売却時期を見極める
また、複数の相続人がいる場合は遺産分割の方法を事前に調整しておくことも大切です。
合意形成をしておくことで手続きがスムーズになり、不要なトラブルや課税を避けられます。
まとめ
相続不動産を売却する際に確定申告が必要かどうかは、売却益の有無や特例の利用によって決まります。
適切に申告することで余計な税負担やペナルティを避けられるだけでなく、控除や加算制度を使って節税につなげることも可能です。
特に「空き家の3,000万円控除」や「相続税の取得費加算」といった制度は、要件や期限を正しく理解していないと活用できません。
相続不動産の売却では金銭面だけでなく、相続人同士の合意形成や手続きの進め方も重要になります。
だからこそ、早い段階で税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談し、客観的な視点を取り入れることを強くおすすめします。
相続は「お金」と「気持ち」の両方を扱うものだからこそ、専門家の力を借りながら冷静かつ円滑に進めていくことが、安心と納得につながります。