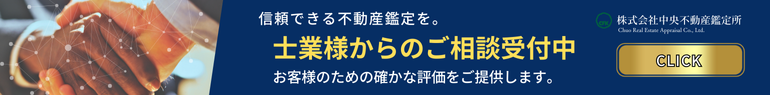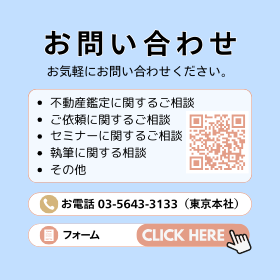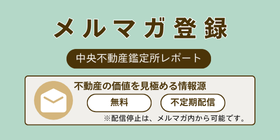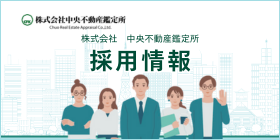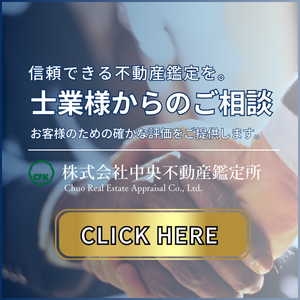不動産の生前贈与とは、生きているうちに不動産の所有権を家族や第三者に無償で譲り渡すことを指します。
相続を待たずに財産を移転できるため、節税やトラブル防止などの目的で活用する方が増えています。
本記事では、不動産の生前贈与の仕組みや手続き、相続との違い、そして節税効果について詳しく解説します。
不動産の生前贈与とは
不動産の生前贈与は、財産を生前に譲渡することで税金対策や資産分配を計画的に行う方法です。
相続による承継とは異なり、贈与時点で所有権が移転するため、家族間の意志を反映しやすく、将来的なトラブルを防止できます。
また、税制度上の特例や控除を活用することで、贈与税や相続税の負担を軽減することも可能です。
生前贈与が選ばれる背景
生前贈与が注目される背景には、税負担の最適化と財産分割の明確化があります。不動産の相続では評価額に基づいて相続税が課されますが、あらかじめ贈与しておくことで特定の控除制度や非課税枠を利用できる場合があります。
また、贈与者が健在のうちに不動産を譲ることで、遺産分割協議を巡るトラブルを未然に防げる点も大きな利点です。さらに、家賃収入を早期に次世代へ引き継ぐことで、資産活用を効率化できるというメリットもあります。
不動産を生前贈与する目的
不動産の生前贈与には、主に相続税対策と財産承継の円滑化という2つの目的があります。贈与によって受贈者に所有権が移転すれば、固定資産税の負担や家賃収入の権利も同時に引き継がれます。
また、高齢化に伴う認知症リスクを見据え、判断能力があるうちに財産を整理しておく意図も含まれます。特に婚姻期間20年以上の配偶者に対しては、居住用不動産の贈与に関する特別控除(上限2,000万円)が認められており、一定の条件を満たせば税負担を抑えることが可能です。
生前贈与の手続きと準備
不動産の生前贈与を行う際は、贈与契約書の作成、登記変更、贈与税申告といった複数の手続きが必要です。登記事項証明書や固定資産評価証明書などの書類を準備し、法務局で名義変更登記を行います。その際、登録免許税を納める必要があり、贈与税が発生する場合は申告期限内に申請を行わなければなりません。
また、不動産を贈与した場合には不動産取得税(地方税)が課される点にも注意が必要です。手続きは複雑なため、税理士や司法書士などの専門家に相談することが望ましいでしょう。
不動産の生前贈与と相続の違い
不動産を生前贈与する場合と相続で承継する場合とでは、税制・手続き・評価方法などに明確な違いがあります。
税金面での違い
生前贈与には「贈与税」、相続には「相続税」が適用されます。贈与税は税率が高めですが、年間110万円の基礎控除や「相続時精算課税制度」を活用すれば、一定の非課税枠を確保できます。一方、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があり、多くのケースで税負担は軽くなります。
2024年からは、暦年贈与の「生前贈与加算」期間が従来の3年から段階的に7年へ拡大されています。相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、長期的な相続対策を検討する際には、この「7年ルール」を考慮することが欠かせません。
登記や特例の違い
登記手続きにも違いがあります。生前贈与の場合は贈与契約書を基に名義変更登記を行い、登録免許税が課されます。相続では相続登記を行いますが、「小規模宅地等の特例」により、一定条件を満たせば土地評価額を最大80%減額できます。
この特例は“相続税の計算上の評価額”を減額する制度であり、登録免許税や不動産取得税といった登記・取得時の税負担を直接軽減するものではありません。特例の可否は相続時の節税効果に大きく影響します。
生前贈与と相続が向いているケース
生前贈与は、不動産の価値上昇が見込まれる場合や、家賃収入を早めに次世代へ引き継ぎたい場合に有効です。また、将来の認知症リスクや家族間の紛争を避けたい場合にも適しています。
一方、基礎控除内で収まる資産規模や、小規模宅地等の特例を活用できるケースでは、相続の方が税負担を抑えられることがあります。不動産の種類や保有状況に応じて、どちらが有利かを慎重に見極めることが大切です。
不動産の生前贈与のメリットとデメリット
生前贈与の最大のメリットは、財産を生前に確実に引き継げる点です。遺言書を作成するよりも明確に意思を反映でき、相続時の争いを防ぐ効果があります。また、相続財産を減らすことで相続税の負担を軽減できる可能性があります。
さらに、家賃収入を受け取る権利を早期に移転すれば、世代間での資産循環を促進できます。
一方で、贈与税の税率は相続税よりも高く、登録免許税や司法書士費用などの諸費用が発生します。さらに、一度贈与した不動産を取り戻すことは難しく、将来の介護や生活資金に影響する可能性もあります。これらのリスクを理解したうえで、計画的に贈与を進めることが重要です。
節税効果を高める制度の活用
節税を目的に生前贈与を行う場合、「相続時精算課税制度」の活用が効果的です。この制度を使えば、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与のうち、累計2,500万円までが非課税になります。
2024年以降は、相続時精算課税を選択している場合でも年110万円の基礎控除が新設されており、控除後の残額のみが相続時に加算される形に改善されています。制度の使い勝手は向上していますが、選択後は原則として撤回できないため、適用可否は慎重に判断する必要があります。
また、毎年110万円までの暦年贈与を継続的に活用する方法も有効です。長期的に少額ずつ贈与を行うことで、税負担を抑えつつ資産を移転できます。ただし、形式的な書類作成を怠ると「実質的に相続財産とみなされる」可能性があるため、契約書の保管や入出金記録の管理が重要です。
贈与後の管理と注意点
不動産を贈与した後は、受贈者が固定資産税の納付や維持管理を行う必要があります。賃貸物件であれば、修繕や入居者対応なども含まれるため、管理体制を整えておくことが重要です。贈与契約書や登記関連書類は、将来的な証拠資料として保管しておきましょう。家族間での認識のズレを防ぐためにも、事前の話し合いと記録の共有が欠かせません。
不動産の生前贈与を成功させるポイント
不動産の生前贈与を円滑に行うには、税務や登記に関する正確な知識と計画性が求められます。制度を誤って利用すると、想定外の課税やトラブルが生じる可能性もあるため、
税理士や司法書士に加え、不動産鑑定士のサポートを受けることが有効です。不動産鑑定士による評価は、贈与時点の時価を明確にし、贈与税や相続税の計算根拠として信頼性の高い資料となります。適正な評価をもとに贈与計画を立てることで、節税効果を最大化しながら安心して手続きを進めることができます。
まとめ
不動産の生前贈与は、相続を待たずに財産を引き継ぐための有効な方法です。節税やトラブル防止など多くのメリットがある一方で、贈与税や手続き費用といった負担も伴います。2024年以降は暦年贈与の加算期間が7年に延長され、相続時精算課税にも新たな控除が設けられるなど、制度が変化しています。こうした最新ルールを踏まえ、贈与・相続それぞれの税負担や費用、将来の管理体制を総合的に比較検討することが重要です。
不動産は評価方法によって税額が大きく変わる資産です。不動産鑑定士に依頼することで、評価額に納得感を持ち、贈与税や相続税の算定を正確に行うことができます。客観的な専門家の意見を取り入れることで、家族間の公平性を保ちながら、安心して財産を引き継ぐことが可能になります。
▶︎不動産相続を成功に導くために不動産鑑定を利用する4つのメリットとは?