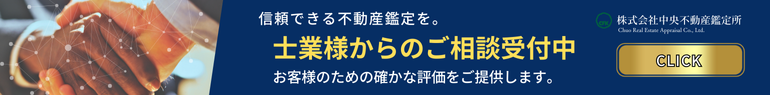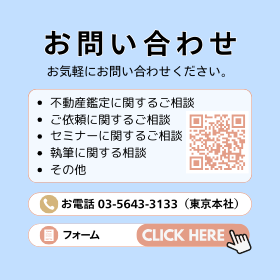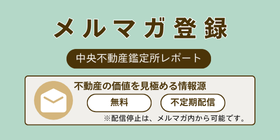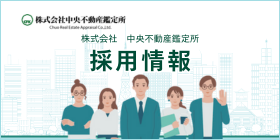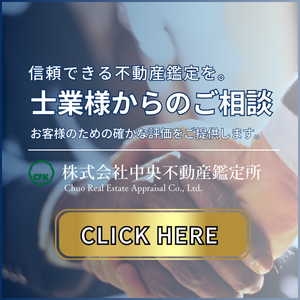「親が亡くなったけれど、地方の空き家を相続するべきか悩んでいる」
「住宅ローンが残っている実家を相続したくない」
「使い道のない山林や農地を押しつけられそうで困っている」
不動産を相続することになったとき、多くの人が直面するのが「相続放棄をすべきかどうか」という悩みです。
特に、価値が低い不動産や負債を抱えた物件を相続してしまうと、金銭的・法的なリスクを背負うことにもなりかねません。
この記事では、不動産の相続放棄について、手続きの流れ、費用、注意点、そして専門家の活用法まで網羅的に解説します。
相続放棄を検討している方、今まさに不動産を相続するかどうか迷っている方は、ぜひ最後までお読みください。
不動産相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がずに放棄する手続きです。不動産の放棄も、原則としてこの「相続放棄」によって行います。
ここで重要なのは、「不動産だけを選んで放棄することはできない」という点です。現金・預金・有価証券・不動産・借金などすべての財産・負債をまとめて放棄する必要があります。
相続放棄の特徴
- 家庭裁判所での手続きが必要
- 被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に申述
- 放棄すると一切の相続権が消滅
- 一度放棄すると原則として撤回不可
こんな時は要注意!不動産相続放棄を検討すべき代表的なケース
住宅ローンが残っている不動産
ローン残債が評価額を上回っている不動産を相続すると、返済義務まで引き継ぐ可能性があります。
老朽化した空き家・遠方の土地
管理費・修繕費・固定資産税などが継続して発生し、将来的にトラブルになることも。
使い道のない山林や農地
農地法や森林法による制限で売却・活用が難しく、管理放棄が問題になるケースもあります。
相続放棄の手続きの流れ|家庭裁判所での申述方法
タイムリミットは「3ヶ月」
被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申述します。
手続きの流れ
- 相続放棄申述書を入手(家庭裁判所またはWeb)
- 必要書類を準備
- 家庭裁判所に郵送または持参で提出
- 裁判所からの照会書に回答
- 「相続放棄申述受理通知書」が届けば完了
必要書類とその取得方法|市役所で揃えるもの一覧
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
| 死亡記載のある戸籍謄本 | 市区町村役所 | 出生から死亡まで連続したもの |
| 住民票の除票 | 市区町村役所 | 最終の住所を確認 |
| 相続放棄をする人の戸籍謄本 | 市区町村役所 | 相続関係の証明用 |
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所 or Web | 誤記に注意し署名押印必須 |
参照: 裁判所
相続放棄にかかる費用|自分で行う場合と専門家に依頼する場合
自分で行う場合の費用目安
- 収入印紙:約800円
- 郵送費・書類取得費:約2,000~3,000円
- 合計:約3,000〜5,000円程度
専門家に依頼する場合の費用
- 司法書士:3万円〜7万円
- 弁護士:5万円〜15万円
相続放棄の注意点|よくある落とし穴とその対策
放棄前にも「財産の保存義務」がある(民法940条)
相続放棄をしていなくても、申述が受理されるまでは「相続人」としての地位にあるため、財産を適切に管理する義務があります。放置して損害が発生すると責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。
放棄によって他の相続人に権利・義務が移る
自分が放棄すると、その分の相続権は次順位または他の相続人に移ります。事前に親族間で協議しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
相続財産を使うと「単純承認」になる可能性
申述前に不動産を使用・売却したりすると、相続を認めたとみなされる「単純承認」扱いになり、放棄できなくなる恐れがあります。財産には触れず、手続き完了まで静的に保つことが重要です。
固定資産税は1月1日時点の名義人に課税される可能性がある
不動産に対する固定資産税は毎年1月1日時点の名義人に課税されます。放棄が年明け以降に受理された場合でも、課税通知が届く可能性があるため、市区町村への説明や証明書の提出が必要になることもあります。
参照:主税局
相続土地国庫帰属制度との違い
相続によって土地などの不動産を引き継ぎたくない場合、選択肢として「相続放棄」と「相続土地国庫帰属制度」があります。
両者は目的こそ似ていますが、手続き先や対象範囲、費用や要件などに大きな違いがあります。以下に主な違いを整理しました。
| 比較項目 | 相続放棄 | 国庫帰属制度 |
| 対象 | 財産全体 | 土地のみ(建物不可) |
| 手続先 | 家庭裁判所 | 法務局(審査あり) |
| 要件 | なし | 境界明確・建物なし・担保なしなど |
| 費用 | 数千円程度 | 約12万円〜(申請+負担金) |
引用:法務省
よくある質問(FAQ)
- 相続放棄は後から撤回できますか?
原則不可です。裁判所が誤認などの特例を認めた場合に限り、まれに認められることがあります。 - 放棄しても役所から管理通知が来ることは?
あります。「相続放棄申述受理通知書」を提出し、放棄済であることを説明しましょう。 - 放棄した不動産に住み続けることはできますか?
できません。不動産を利用する行為は「単純承認」とみなされ、放棄が無効になるおそれがあります。
専門家に相談するメリットと選び方
相続放棄の手続きは自分でも対応できますが、状況によっては専門家の力を借りたほうがスムーズかつ確実です。
書類の不備を防げる
戸籍の抜けや記載ミスなどで再提出となるケースは少なくありません。専門家に任せることで正確な申述が可能になります。
相続人が複数いる場合の調整も安心
相続人間の利害がぶつかる場合、司法書士や弁護士が中立的な立場で調整役を担うことでトラブルを防げます。
放棄後の管理や税務処理にも対応
放棄が認められた後も、自治体とのやり取りや必要書類の提出など実務対応が必要です。専門家に依頼しておくことで安心して任せられます。
それぞれの専門家の役割
- 司法書士:申述書の作成・提出代行・登記手続きまで対応
- 弁護士:相続人間の紛争対応・遺産分割協議の代理人も可
- 不動産鑑定士:相続対象の不動産価値を客観的に評価。不動産の売却や放棄判断の材料として不可欠です。
まとめ|不動産相続放棄で将来のリスクを減らす第一歩を
不動産相続放棄は、将来的な税負担や管理義務を避けるための有効な選択肢です。ただし、正しい知識と手順を知らなければ、かえってトラブルや余計な支払いにつながる可能性もあります。
必要書類の準備や法務局での手続きは一見煩雑に思えるかもしれませんが、ポイントを押さえて進めれば、自分でも対応できる内容です。
不安な場合は司法書士や不動産関係の専門家に相談しながら、確実かつスムーズに手続きを進めることをおすすめします。
大切な財産を適切に引き継ぐために、相続不動産の名義変更をしっかりと行い、安心できる未来に備えましょう。
不安がある方は、税理士や司法書士、不動産鑑定士などの専門家に相談することで、より安心・安全な手続きを進めることができるでしょう。
▶︎不動産相続を成功に導くために不動産鑑定を利用する4つのメリットとは?