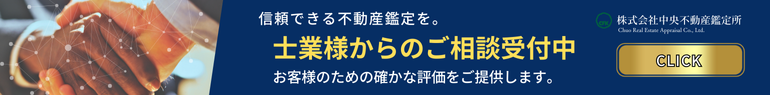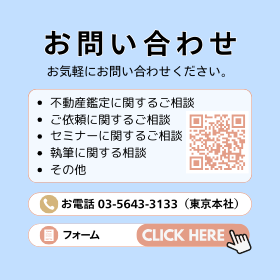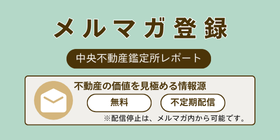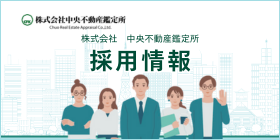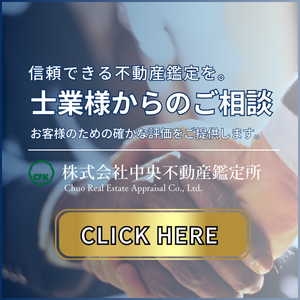余命宣告を受けた後、多くの方がまず考えるのは「家族にできるだけ迷惑をかけたくない」という思いです。
残された時間の中で、財産や不動産をどのように整理し、相続税の負担をどこまで軽減できるかは、多くの家庭にとって大きな課題となります。
相続税の仕組みや最新の制度改正を理解し、限られた時間の中でできる現実的な対策を講じることで、家族の不安を少しでも和らげることができます。
本記事では、余命宣告後でも実行可能な相続税対策の基本と、専門家を交えた効果的な準備の進め方を詳しく解説します。
余命宣告後に考えるべき相続税対策とは?
相続税とは、被相続人が亡くなられた際に、その遺産に課される税金のことです。
課税額は「課税価格合計額」から「基礎控除額」を差し引いて算出されます。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、例えば法定相続人が1人の場合は3,600万円が控除されます。基礎控除を超えた課税遺産総額に応じ、税率が10%から55%の範囲で適用されます。
また、余命宣告後の対策で注意すべきなのが生前贈与です。贈与税は年間110万円を超える贈与に課税されますが、一定条件を満たせば「相続時精算課税制度」を利用することで合計2,500万円まで贈与税が非課税となります。
ただし、2024年1月以降は相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるため、新制度を踏まえた計画的な対応が必要です。
余命宣告後に特に重要なポイント
余命宣告後は、時間的制約があるため慎重かつ迅速な判断が求められます。最も重要なのは、被相続人自身が納得できる形で財産分配を決めることです。
そのためには、遺言書の作成と、相続税を可能な限り抑えるための具体的な対策を早期に検討する必要があります。
遺留分を考慮したうえで、非課税枠の活用や不動産の購入、公益法人への寄付なども有効です。
また、お墓や仏壇といった課税対象外の財産に充てることも一つの方法です。相続税の金額を下げるだけでなく、家族間のトラブルを防ぐ視点も欠かせません。
税理士との連携によるスムーズな対策
余命宣告後の相続税対策では、税理士との連携が欠かせません。
相続税や贈与税の実務に詳しい税理士は、適切な申告や節税策を提案してくれます。
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内と定められており、この間に遺産分割協議や財産評価を終える必要があります。
税理士の支援があれば、期限内の手続きを円滑に進めることができ、納税資金の確保や不動産評価の見直しもスムーズに行えます。
余命宣告後に活用できる相続税の特例
余命宣告後でも利用できる相続税の特例にはいくつかの選択肢があります。
代表的なものが「小規模宅地等の特例」です。被相続人が居住や事業で使っていた土地について、一定条件を満たせば相続税評価額を最大80%減額できます。
また、生命保険金の非課税枠も有効です。法定相続人1人あたり500万円までが非課税とされ、計画的に活用することで税負担を軽減できます。
さらに、公共団体や公益法人への寄付を行えば、寄付財産は非課税扱いとなることもあります。これらの特例は、条件や手続きが複雑なため、専門家と相談しながら進めることが重要です。
生命保険を活用した相続税対策
生命保険金には「法定相続人の数×500万円」の非課税枠が設けられています。
例えば法定相続人が3人なら、1,500万円まで非課税です。この制度を活用すれば、相続税の課税対象を減らし、家族の生活資金を確保できます。
ただし、非課税枠の対象は受取人が法定相続人である場合に限られます。
相続人以外を受取人に指定すると課税対象になるため注意が必要です。
契約者・被保険者・受取人の関係を「被保険者=契約者=被相続人」「受取人=法定相続人」とするのが最もシンプルで、非課税枠を最大限に活用できます。
生前贈与の活用と注意点
生前贈与には暦年贈与と相続時精算課税制度の2種類があります。暦年贈与は年間110万円まで非課税で、数年かけて計画的に贈与することで相続税の負担を減らせます。一方、相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子や孫に贈与する場合に適用でき、2,500万円まで非課税となります。
ただし、2024年以降は贈与から7年以内に相続が発生した場合、その贈与が相続財産に加算されます。
余命宣告後に短期間でまとまった贈与を行うと、結果的に課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
教育資金贈与や結婚・子育て資金贈与の非課税制度を利用すれば、子や孫への資産移転を効果的に進められます。非課税限度額や手続き条件を理解し、税理士と相談しながら進めることが重要です。
▶︎不動産の生前贈与は得?損?相続との違いと節税効果を徹底解説します。
遺言書と相続放棄による柔軟な備え
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、それぞれに特徴があります。
形式不備を防ぎたい場合は、公証役場で作成する公正証書遺言がおすすめです。費用は財産額に応じて数万円程度で、法務局に保管すれば紛失の心配もありません。
また、相続財産に借金が含まれている場合は、相続放棄という方法もあります。家庭裁判所に申請し、相続開始から3か月以内に手続きを行えば、相続人としての責任を免れることができます。プラスの財産とマイナスの財産を整理し、家族間でよく話し合うことが大切です。
家族との対話と専門家への相談
余命宣告後は、財産だけでなく家族の気持ちの整理も重要です。財産の分け方や今後の生活について率直に話し合うことで、家族間の誤解を防げます。一度にすべてを決める必要はなく、複数回に分けて話し合うのが現実的です。
税理士や弁護士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家を選ぶ際は、実績と対応姿勢を確認し、自分たちの状況に寄り添ってくれるかを見極めましょう。
特に不動産を含む相続では、資産評価の正確さが節税に直結します。必要に応じて不動産鑑定士へ相談し、客観的な評価をもとに計画を立てることも有効です。
まとめ
余命宣告を受けた後でも、相続税対策は十分に間に合います。
まずは遺言書を整え、生命保険や生前贈与の活用を検討しましょう。
不動産を含む財産がある場合は、不動産鑑定士に評価を依頼することで、適正な価格をもとにした正確な相続税計算が可能になります。税理士や弁護士と連携しながら早めに準備を進めることが、家族の安心と節税の両立につながります。残された時間を有効に使い、家族への思いを確実な形で残すことが大切です。
▶︎不動産相続を成功に導くために不動産鑑定を利用する4つのメリットとは?