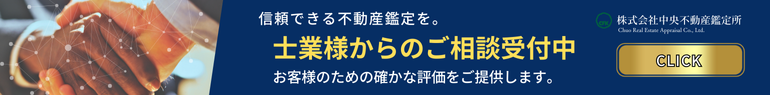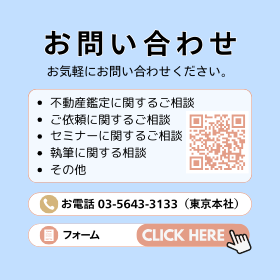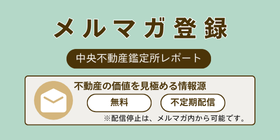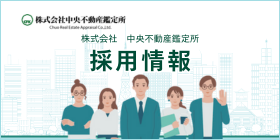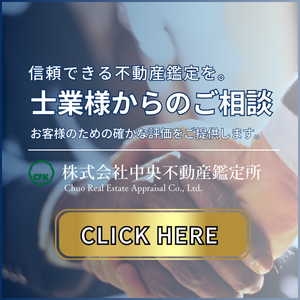親族への相続と聞くと、「配偶者」や「子ども」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし近年、「孫に不動産を残したい」と考える高齢の方も増えてきています。
理由はさまざまです。すでに子どもは経済的に自立している、孫の教育や生活を支援したい、生前から強い絆を感じているなど、
そんな思いから、孫への相続を希望するケースが少なくありません。
とはいえ、孫は法律上の“法定相続人”には含まれず、そのままでは不動産を相続させることができません。
民法や税法の知識が不可欠であり、事前の準備がなければ思わぬトラブルや税負担が発生することもあります。
この記事では、「孫に不動産を相続させたい」と考える方向けに、その方法、注意点、必要な手続きについてわかりやすく解説します。
孫に不動産を相続させる基本的な考え方
法律で定められた相続人である「法定相続人」には、配偶者、子、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹などが含まれます。
一方で、孫は特別な条件を満たさない限り、法定相続人には含まれません。
したがって、孫に不動産を相続させるには、法的な措置を講じる必要があります。
ただし、孫が不動産相続をする可能性として、両親が存在しない場合などに代わりに相続権を得るケースが挙げられます。
法定相続人以外の孫が遺産相続を受けるには、遺言書を作成する、養子縁組を行うなど、計画的な準備が不可欠となります。
代襲相続の仕組みと孫が相続できるケース
孫が祖父母の財産を相続できる状況の一つに、代襲相続があります。
代襲相続とは、本来相続人である子が相続開始時点ですでに亡くなっている場合、
その子に代わって孫が相続人となる制度です(民法第887条第2項)。
この制度では、孫が相続人として認められるため、相続税の2割加算の対象外になります。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害していないかの確認が不可欠です。
事前に専門家へ相談し、代襲相続が発生する可能性を見据えて対策を講じておくことが望ましいでしょう。
引用:国税庁
孫への相続と遺留分の関係
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、相続人が最低限もらえる取り分のことです。
たとえば、ある人が「全財産を孫にあげる」と遺言を残しても、配偶者や子どもなどの法定相続人には、法律で保障された取り分(=遺留分)があります。
つまり、遺留分は「家族の最低限の相続権を守る仕組み」です。遺言や贈与をする際には、この遺留分に配慮することが大切です。
被相続人の意思による自由な遺産分配を制限する制度で、配偶者・子・直系尊属に対して認められています。
たとえば、不動産全体を孫に相続させるという遺言があった場合でも、法定相続人の遺留分を侵害していれば「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。
つまり、孫に不動産を与えること自体は可能ですが、その結果として配偶者や子どもが自分の取り分を失うような形になると、法的なトラブルが発生しかねません。
このようなリスクを避けるためには、遺留分を考慮した遺言書の作成や、事前の家族間の話し合い、専門家のアドバイスを踏まえた遺産分割計画が非常に重要です。
孫に不動産を相続させる方法と手段とは
【遺言書の作成】
遺言書は孫に不動産を相続させるための有効な手段の一つです。孫は通常、祖父母の法定相続人ではありませんが、遺言書を活用することで、特定の財産を孫に遺贈することが可能です。
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」などの種類がありますが、トラブルの防止を考慮するなら、法的効力が強く、作成の信頼性が高い公正証書遺言の利用が推奨されます。また、遺言書を作成する際には、遺留分の問題に配慮することが重要です。他の相続人の遺留分を十分に考慮しない内容で遺言書を残すと、遺留分侵害請求に発展する可能性があるため、注意が必要です。
さらに、遺言書の内容が明確でない場合、手続きに混乱を招き、最終的に遺産相続のトラブルに発展する可能性もあります。そのため、内容をしっかりと詰めるだけでなく、経験豊富な専門家への相談がおすすめです。
また、孫は法定相続人ではないため、「相続」ではなく「遺贈」として指定されることになります。
確実に意思を実現するためには、遺言書の作成前に専門家に相談することをおすすめします。
詳しい遺言書の作成方法は政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」をご確認ください。
【生前贈与】
生前贈与は、相続発生前に不動産を移転できる合法的な手段です。贈与税が発生する可能性はありますが、「暦年贈与(年間110万円以下は非課税)」や「相続時精算課税制度(最大2,500万円まで非課税)」を活用すれば、税負担を軽減できます。
暦年贈与では、毎年110万円以下の金額であれば贈与税がかかりません。
ただし、この制度を継続的に使う際は、毎年の贈与契約書を作成し、受贈者(孫)が実際に自由に管理・使用できる状態であることが重要です。これを怠ると、後に「名義預金」や「相続財産」とみなされて、課税されるリスクがあります。
さらに、不動産を贈与する場合は、贈与税以外にも登録免許税(不動産の評価額の2%)や不動産取得税(同3〜4%)が発生します。これらの諸費用を含め、全体の負担を試算したうえで贈与のタイミングや金額を計画することが大切です。
【相続時精算課税制度の活用】
この制度を利用すると、贈与者1人につき2,500万円まで贈与税がかからずに財産を移転できます。ただし、一度選択すると暦年課税に戻れないという制約があり、不動産の将来的な価値上昇も考慮すべきです。
たとえば、祖父母から孫に不動産を贈与する場合、不動産の評価額が2,500万円以内であれば贈与税はかかりません
(その代わり、相続時に贈与分が相続財産に加算されます)。
この制度は、将来の相続税を見据えて早めに財産を移したい場合に有効ですが、
以下の点に注意が必要です
- 贈与時点での不動産評価額が相続時よりも大きく値上がりしていた場合、相続税が増える可能性があります。
- 不動産の名義変更時には登録免許税・不動産取得税が発生します。
- 税務署への届出が必要で、贈与者・受贈者の年齢要件にも条件があります。
引用:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
【養子縁組】
孫を養子とすれば、法律上の子として法定相続人に位置づけられます。これにより、遺留分の権利も発生し、相続の安定性が増します。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが、
相続対策に用いられるのは通常「普通養子縁組」です。
孫を養子にすることで、実子と同様に法定相続人となり、相続税の基礎控除の計算にも含めることができます。
ただし、相続税法上で相続人として認められる養子の人数には制限があります(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)。これを超える養子は、相続税の計算上カウントされません。
また、他の相続人との関係悪化を防ぐため、家族間での事前の話し合いや理解を得ることが大切です。戸籍上の変更手続きや住民票の整備も必要となるため、司法書士や行政書士に相談しながら進めましょう。
税金と手続きの注意点
相続税の2割加算について
孫が代襲相続人として相続する場合には通常の相続税率が適用されますが、
そうでない場合には相続税額に20%の加算が課されます(相続税法第18条)。
この加算は、法定相続人でない者に対する優遇措置がないことを意味しており、たとえば遺言によって孫に不動産を相続させた場合などが該当します。
たとえば、課税遺産総額が1,000万円で相続税額が100万円であると仮定すると、孫が代襲相続人でない場合には、相続税額が120万円になります。これは単純な2割加算ですが、相続全体の税額に与える影響は大きく、事前の税額シミュレーションが欠かせません。
さらに注意すべきは、相続税の申告義務がある場合、2割加算の対象となる孫についても他の相続人と同様に期限内(原則として相続開始から10か月以内)に申告と納税を行う必要がある点です。加算の対象であることを失念していると、追徴課税や延滞税が課されるおそれもあります。
また、2割加算が適用されるかどうかは形式だけでなく、実態に基づいて判断されることもあるため、孫が代襲相続人にあたるか否かについても、戸籍や被相続人の死亡状況などを正確に確認しておくことが重要です。
相続税の加算対象であるかどうかの判断や課税額の見積もりに不安がある場合は、早めに税理士に相談し、正確な納税計画を立てることが推奨されます。
【登録免許税と不動産取得税】
不動産取得税は相続による取得には非課税ですが、名義変更に伴う登録免許税が発生します。税率は不動産の固定資産評価額に対して0.4%。例として評価額3,000万円なら12万円が必要となります。
孫への不動産相続で注意すべきリスク
・他の相続人とのトラブルを防ぐために、理由を明記した遺言書が有効
・自筆証書遺言の不備による無効リスクへの対応(公正証書遺言を推奨)
・生前対策をしないと、相続時の混乱が生じやすい
トラブル防止には、理由を明確にした遺言書の作成と生前からの家族との対話が欠かせません。
公正証書遺言で形式面のリスクを防ぎ、専門家の協力を得ることが安心への近道です。
まとめ
孫に不動産を相続させるには、民法や税法に基づいた慎重な計画と準備が不可欠です。
代襲相続・遺言書・生前贈与・養子縁組といった手段を組み合わせながら、
トラブルや課税リスクを避けるためにも、専門家の助言を得て進めることが望ましいでしょう。
不安がある方は、税理士や司法書士、不動産鑑定士などの専門家に相談することで、より安心・安全な手続きを進めることができます。
▶︎ 不動産相続を成功に導くために不動産鑑定を利用する4つのメリットとは?